![]()
日本音楽には西洋音楽における主音のように、ある一つの音が音階の第一音であるとともに終止音となって、音楽の中で中心的役割を果たす、という音階構造は持たない場合が多いとされる。それに伴い、1オクターブ内で等しく重要な音が数個あり、それを「核音」とする理論が優勢である。しかし、私自身の演奏・鑑賞体験から、例えば、尺八古典本曲では「核音」という考え方のほうがよいが、地唄においては、主音が(従って調性も)あり、その上で転調が行われている、と感じるようになったため、この論考を試論としたい。
Ⅰ 主な音と調性の構造
1.トニック (主音)
その曲の終止音。尚、それを中心にした音階による調性を主調(ファンダメンタル・キー)と呼ぶ。具体的には下降終止音形、上向終止音形によって判断する。
日本の近世音楽の場合、下降終止の場合短二度、上向終止の場合長二度の音程で主音に終止する。例えば「夕顔」の場合トニックは D (音名はドイツ音名)であるので
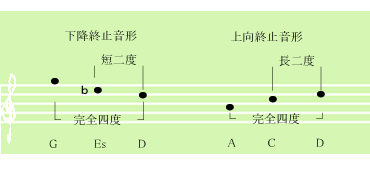
となる。もちろんモティーフ(動機)単位では単に Es→D、C→D の二音だけで判断することも可能である。何故3音単位で示しているかというと、この音形で出てくることが圧倒的に多いことが一つ、もう一つは後に述べる半終止からのサブドミナント→トニック、ドミナント→トニックへの解決を下降終止音形、上向終止音形はそれぞれ意味しているからである。
トニックの長二度下の音(この場合 C)を「導音」、短二度上の音(この場合Es)を「上主音」と呼ぶ。
一点、注意しておきたいのは、曲の中で調絃が変わる場合、曲の終止音が、曲全体の主音とはならない場合があることである。主音は、ほとんどの場合、調絃によって決まる(というよりも、調性によって調絃を変える)。詳しくは「調絃とその特性」を参照。
2.ドミナント (属音)
トニックの完全五度上(完全四度下)の音。尚、それを中心にした音階による調性を属調(ドミナント・キー)と呼ぶ。ドミナントでモティーフが終止したとしても、転調していない場合があり、その終結のことを半終止という。
トニックは当然安定性、終止性という感覚を与える。それはその曲の中心音による終止ということから自明のことである。
これに対しドミナントは不安定性、流動性という感覚を与える。ドミナントからトニックに回帰することによって緊張→安定という音楽の流れを形作る。経験的、生理的にドミナントはトニックへの回帰へのあこがれ・期待感を人に与える。そのためトニックに回帰せずドミナントでの半終止を基本としたままメロディーをつづけると欲求不満となり、トニックへのあこがれがつのる。この手法はワーグナーが使用したものが典型的なものである(無限旋律とよばれている)。
ドミナントへの半休止:トニック=D の場合(例:「夕顔」等)
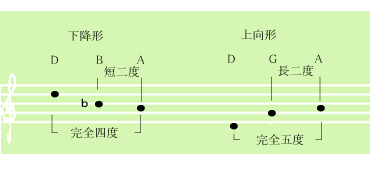
ドミナントでの完全終止との区別について。上向形の場合 D が E になるため簡単に区別できる。下降形の場合は曲の流れから判断するが、ポイントはドミナントの音階にあり、トニックの音階にはない
E の音が前後にあるかどうかである。E でなくトニックの音階にある Esである場合はドミナントへの半終止と考えてよい。その場合、何らかの形で
D へ終止することが多い(そうでない場合、何らかの作曲上の意図があるということになる)。
音階については後述する。
3.サブドミナント (下属音)
トニックの完全四度上(完全五度下)の音。尚、それを中心にした音階による調性を下属調(サブドミナント・キー)と呼ぶ。地唄の場合、下属調への転調は三絃の機能的には多少すんなりとはいかない(詳しくは「調絃とその特性」で後述する)。そのため下属調への転調には解釈上特に注意を要する。それだけの意味があると考えられるからである。
サブドミナントへの移行形:トニック=D の場合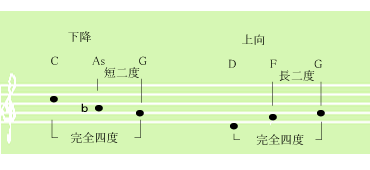
下降形の場合3音で現れることはまず無い。例えば G・Es・D・C・As→G のようにあるメロディーの終止部という形の中で出てくる。あるいは、突然
As を出して G へ下降終止する。
Ⅱ 音 階
一般に、近世邦楽の音階とされる都節の説明から始める。
1.都節の基本形
都節の分析としては、二つのテトラコルドの結合で説明される。テトラコルドとは、「核音」という考え方から出るもので、民俗音楽研究の第一人者:小泉文夫氏が、都節のみならず、あらゆる日本音楽の音階構造の分析方法として、テトラコルドを基に考察している。具体的には、完全四度をなす二つの核音の中に中間音一つ、というものである。
都節の場合、下の核音から短二度上に中間音を持つとされる。DとG、AとD、二つのテトラコルドに中間音を含めると、それぞれ〔D・Es・G〕、〔A・B・D〕となり、都節はこの二つのテトラコルドの結合(この場合、AとGが長二度音程なので、ディスジャンクトと呼ばれる接続方式による)と考えられる。従って〔D・Es・G・A・B・D〕が都節音階の基本形ということになる。
具体例を挙げれば、「さくら、さくら」を考えるには、基本形の都節で十分である。
2.ドミナント→トニックへの解決から導き出される二つの四音音列
それでは、地唄に「主音」という概念があるとして考察してみる。前述のとおり、調性音楽はドミナント→トニックと解決することによって推進力を得る。そこで音階がなぜ生まれたか明らかにするために、音階を二部分に分けて考えることにする。
① ドミナントへの下降半終止→トニックへの上向終止
これまで同様、D をトニックとして例にする。それぞれ〔D・B・A〕、〔A・C・D〕という音形であることはⅠで述べた。ここから音列を導き出すと〔D・C・B・A〕という四音音列になる。
② ドミナントへの上向半終止→トニックへの下降終止
これまた D をトニックとするとそれぞれ〔D・G・A〕、〔G・Es・D〕という音形であることはⅠで述べた。ここから音列を導き出すと〔A・G・Es・D〕という四音音列になる。
3.コンジャンクトによる六音音階
以上2通りのドミナント→トニックの形から導き出された2つの四音音列を統合する(この場合Aは共通のため、コンジャンクトと呼ばれる接続方法による)と
D のトニックの音階ができる。すなわち〔D・C・B・A・G・Es・D〕。
日本音楽=五音音階という先入観は、地唄に関しては危険ではないだろうか。基本形の都節は、近世邦楽のメロディーを考える上では有用だが、地唄に頻出する導音(この場合C)が含まれておらず、少なくとも地唄を考えるには不十分だ。冒頭で述べた、地唄には「主音」というものがある、と私が感じるのは、この頻出する導音の存在によるものである。導音を奇音(音階外の音)として扱うのはどう考えてもおかしい。そこで、基本形の都節以外の音階構造を考察してみたのである。
地唄は以上のような分析から、六音音階に基づいているとも考えうる。
4.上向時嬰羽形の都節
しかし、実際に地唄を聴いた場合に、トニックがDでD・C・B・A、といった旋律形はありえない。メロディーを考えるにはやはり都節は有用なのである。そこで、導音を奇音とするのはおかしいということを解決するために、西洋音楽の旋律的短音階や和声的短音階のように、都節も上向形と下降形を別に考える見解がある。トニックがDの場合、下降形はそのまま、ふたつのヘクサコルドのディスジャンクトによる〔D・B・A・G・Es・D〕として考え、上向形はⅠの1の上向終止音形を取り入れ、〔D・Es・G・A・C・D〕として考える、というものである(AとDのテトラコルドの中間音を、上向の場合Cとする、ということ)。この見解を、日本音楽的に言い換えたのが「上向時嬰羽形」という用語なのである。
この見解ならば、導音を奇音とするということもなくなり、なおかつメロディーを考える場合にも無理がなくなる。したがって「音階」としては、この上向時嬰羽形の都節を採用することとする。
ならばⅡの3で述べた六音音階に意味がなくなるかといえば、そうでもない。「導音」という概念は、「主音」という概念と一体である。したがって、調性という概念も付随する。つまり、「導音」を重視した都節の新見解では、調性の存在を認めうるのであり、六音音階を導き出した考察もひとつの見解であり、たとえばD調の「構成音」は、この6音であるからである(上述の都節の上向形と下降形の組み合わせ)。核音の中でも、導音の存在するものはその部分の主音と考えられるということであり、等しい重要度の核音が数個同時に存在するのではなく、転調によって主音が変わる、と考えられるのである。つまり、特定の音の重要度は部分によって変化する、ということである。
ところで、「音階」と「構成音」の違いを理解していただき、混乱しないよう注意申し上げた上で、Ⅴでは、その調の「構成音」を五線譜で記載することとする。一般論として、「構成音」をそのまま音階とする見解もあるが、上述のとおり、上向形と下降形は別に考えたほうが望ましい。
Ⅲ 調絃とその特性
一の絃=D として考える。
1.本調子 (ほんちょうし)
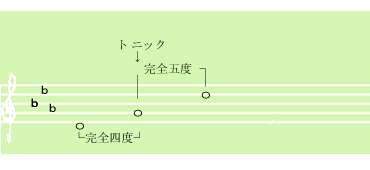
本調子は二の絃をトニックとし、ドミナントで囲むような形になる。ドミナントはトニックへ回帰する性質を持つことは繰り返し述べたとおりである。そのため旋律は二の絃に集束されるような形になるため、曲想は重厚・荘重なものに適している。曲中で何度か調絃を変えるような大曲が本調子で始まるのが多いのは他の調絃への変えやすさ(本調子→二上り→高三下り)もあるが、そうした曲調を求めているとも考えられる。
ところで、本調子(トニック:G)の場合、サブドミナントはCである。C調の演奏には上主音:Des(一と三の開放絃の半音下の音)が不可欠であり、そのため、下属調(C調)の演奏は、G調、D調ほどはすんなりとはいかない。
2.二上り (にあがり)
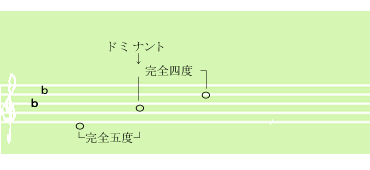
譜例を比較すれば明らかであるが、本調子とは正反対といってよい。ドミナントを二の絃に置き、トニックが両脇にあることにより、曲想は流麗なメロディーのものに適している(ドミナント→トニックというメロディーラインの基本が、上向にも下降にも使えるため)。菊岡は二上りを好んでいると私は思うのだが、その美しいメロディーを考えるにつけ興味深い。
ところで二上り(トニック:D)の場合、サブドミナントはGである。G調の演奏には上主音:As(二の開放絃の半音下の音)が不可欠であり、そのため、下属調(G調)の演奏は、D調、A調ほどはすんなりとはいかない。
3.三下り (さんさがり)
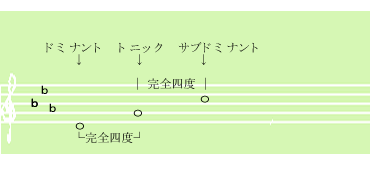
もうこれを見れば三下りの特色は明らかであろう。トニック・ドミナント・サブドミナントの3主要音を持つため、転調をしやすい機能的な調絃である。手事部分や、細やかな転調をする唄部分に適する。
ただ、注意したいのは、三下りの場合、まれにCがトニックになるケース(例:越後獅子の後唄の最後の部分)もあることで、「核音」という考え方が必要なのかもしれない。しかし、越後獅子(全曲通して三下り)にしても、C調は最後の部分だけで、他はG調が主調である。
Ⅳ 調絃の使用例の具体的考察
1.楫 枕 前唄・手事:本調子 → 後唄:二上り
この曲の後唄までの部分は非常に古典的な造りであり(特に手事など段構成にまでしてある上に、「掛合い(特定の旋律部分の応答形式の交互演奏)」もない、というほど徹底している)、菊岡の作曲ではないのではないかという考え方も出てきそうなものだが、私は、これは明らかに菊岡が意図して擬古典的(大坂物的)に作曲したものである、と考える。前唄の部分、特に「しほる思ひを」以下の部分などの抑制された哀しみはまさに本調子にふさわしい品格をもっている。
キーポイントは手事。二段から構成されるが、単に擬古典主義というのではなく、これは西洋バロック変奏曲のドゥーブル変奏(装飾変奏)に相当するものである。ドゥーブルの多く(有名なものでいえば、J・S・バッハの管弦楽組曲第2番のポロネーズなど)は、主題の1/2の音価を単位にして変奏するものであり、楫枕の手事はまさにそれと一致する(段合せをすればそれは容易に理解できる)。そしてこの形式はテンションを高めるのに非常に効果的なのである。
もうおわかりであろう。後唄の儚い願いを表現するコントラストを形成するためだったのである。後唄はもはや抑制された哀しみではない。満を持して二上りになり、菊岡のロマン的表現の世界がくりひろげられるのである。
2.磯千鳥 前唄:低二上り → 手事:三下り → 後唄:本調子
この曲は菊岡の曲の中でもとりわけロマン的な(私は、松浦は時折、奇抜な転調はするが、表現はハイドン的な古典性を持っていると思う。それと比較した意味でという意味である)曲である。まず目につくのは調絃を2回も変えている(中規模曲では異例といっていい)ことと、その変化の仕方。大体の曲は(例えば「(新)青柳」や「笹の露」等)本調子→二上り→高三下り、となっているが、この曲で上記のようになっているのは無論故無きことではない。まず一つは前唄のロマン的表現には二上りが適していること、そしてもっと重要なのは、この曲の大規模な手事にはやはり機能的な三下りを使いたかったからであろう、ということである。そして派生的・結果的に後唄で本調子になったと考えられるが、本調子の品格のある曲想により、この曲がひきしめられているのである。
Ⅴ 記譜について
最後に、五線譜記譜の場合の、フラットの数のことを記して終えることにする。D がトニックとすると、「構成音」は、〔D・C・B・A・G・Es・D〕ということは前に記した。するとここには
B・Es という2つのフラットを持つ音があるため、D がトニックの場合は便宜的に2つフラットを付することとした。故に西洋楽理における g-moll
もしくは B-dur とは全く関係ない。以下は他の例。
音階として考えた場合の上向形と下降形も音名で付記しておく。
※トニック:G → フラット3つ
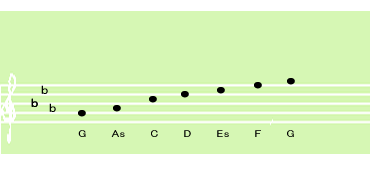
上向形〔G・As・C・D・F・G〕
下降形〔G・Es・D・C・As・G〕
※トニック:C → フラット4つ
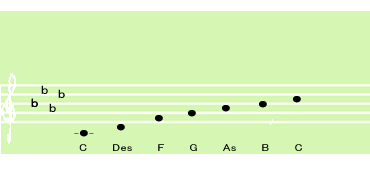
上向形〔C・Des・F・G・B・C〕
下降形〔C・As・G・F・Des・C〕
Copyright©hectopascal All rights reserved